悪い魔術師を倒す勇者を描く物語を
いくつかのパラグラフにわけて読み進んでいく、ゲームブック形式の小説。
kindleのリンク機能を使って実現したもの。
小説としてのストーリーは正直期待外れだったが、
Kindleというプラットフォームでの新しい表現方法には強く感動した。
リンク機能を使って次のパラグラフへジャンプする仕組みは、
まるでノベルゲームを遊んでいるかのようにスムーズに読み進めることができる。
ただ、ゲームオーバーになった際に直前のパラグラフへ戻る機能がないため、
どのパラグラフから遷移したかをメモしておく必要があり、その点は少々手間に感じた。
とはいえ、既存のシステムを想定外の方法で活用した表現を体験できるのは非常に面白い。
値段も手頃なため、創作者の方は一度試してみることをお勧めする。

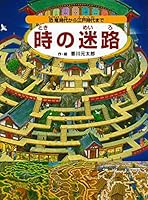







![PMBOK対応 童話でわかるプロジェクトマネジメント[第2版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51n+Im-NE+L._SL200_.jpg)